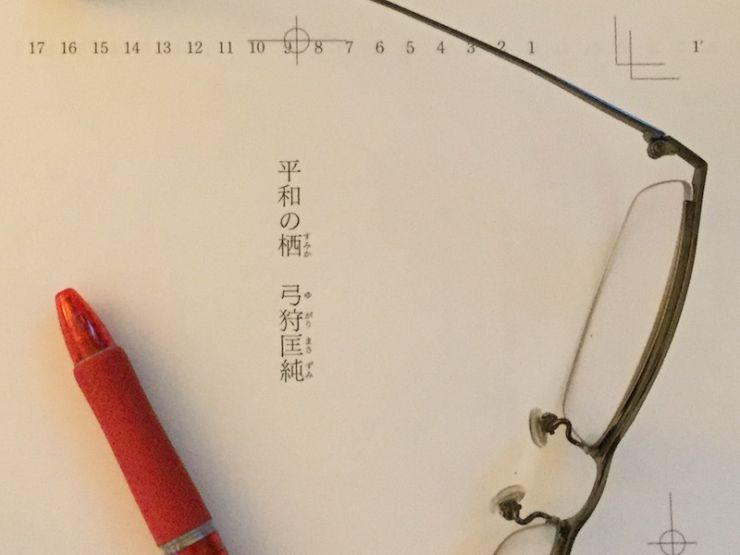
たまには業界話を致しましょう。本のお話です。書籍というものは、作家と編集者だけで作られるわけではありません。なくてはならない存在が校正さんです。まさに縁の下の力持ち。校正さんの力量次第で作品のクオリティが左右されると云っても過言ではないため、作家としては足を向けては寝られません。
昨今、メディア・リテラシーの重要性があちらこちらで論じられるようになりました。フェイク・ニュースはもちろんのこと、マスメディアの報道を鵜呑みにしては行けないと。しかしながら、マスメディアの一員として云わせて頂ければ、メディア・リテラシー云々を論じる以前に、まずもってマスメディアの第一報は、誤報とは云わないまでも不正確な情報を含む記事が決して少なくはないことを理解しておくべきでしょう。特にネットのニュース速報に脊髄反射的に反応するほど愚かなことはありません。
この「不正確さ」を生み出す要因は様々ですが、無視出来ない要素として校閲作業が挙げられます。速報性を重視するテレビはもちろんのこと日刊紙においても校正は、(大型企画を除けば) 誤字・脱字や用字用語の誤り、不適切な表現をチェックするいわゆる文字校正、「赤入れ」に留まります。記事の信頼性や精度に疑問を抱いたデスクが取材のやり直しやリライトを命じることは多々ありますが、出稿までの時間に追われるこれら媒体において、事実関係の確認は記者本人に託されます。
一方、書籍の場合には校正さんが原稿にギッチリ目を通します。ノンフィクションの場合、10年ほど前までは引用した参考文献は巻末にまとめて列記するのが通例でしたが今は、出典を明確にすべく学術論文と同じように本文中にも記載するケースが増えました (私も、書き下ろし作品の場合には数年前からこのスタイルを踏襲しています)。
校正さんは、作家が示した資料のみならず他の文献にもあたり、事実関係を確認します。その上で、上記の赤ペンで書き入れられる「文字校正」以外に、黒鉛筆で「鉛筆出し」を行います(「疑問出し」、「指摘出し」、「ギ出し」とも云います)。他の文献資料に異なった記述があれば「ママOK?」といった形でこれを添付する。つまり明らかな間違いではなく、作家の判断に委ねる”助言”です (云うまでもなく、取材によって得られた"事実"については校閲作業の範疇外となります)。
作家は、当然のことながら自信満々で執筆しています。また、指摘された文献資料もすでに参照した上で「信頼性に疑義アリ」といった判断から採用しなかったケースもあるため、カチンと来ることも少なくありませんが、「確かにその通り!」と得心する指摘も多々あります。実際、曖昧な箇所があっても、筆を止めないためにそのまま書き進め、後で確認するつもりだったが失念していた、といったこともよくあり、そんな折には「よくぞ気づいてくれた!」と思わず手を合わせたくなります。
この「鉛筆出し」、実は出版社さんによって”品質”が大きく異なります。私の作品を刊行して下さった版元さんで云えば、大手出版社である文藝春秋さんや角川書店さんはさすがにレベルが高い。これでもかと云うほど「鉛筆出し」が付されて戻って来ます。これを「採用」するか「却下」するかは作家次第ですが、第三者による客観的なチェックは、ややもすれば独りよがりとなり勝ちな作家に大きな安心感をもたらします。また、この「鉛筆出し」の質と量によって、出版社のスタンスや実力も推し量ることが出来ます。
特に拙著『平和の栖〜広島から続く道の先に』を刊行して下さった集英社クリエイティブさんは、「この作品は今後、広島の戦後復興を取材・研究するにあたり、必ず参考文献として引用されることになるだろう」との考えから通常、校正は初校のみですが、再校でも校正さんが目を通して下さり、原稿チェックだけでも約3ヶ月を要しました。
一般読者には無縁の世界ですが、こうした地道な編集・校閲作業が我が国の出版文化を支えている、と云っても過言ではありません。いくらネットが幅を効かせようが、書籍は決してなくならない、と信じる理由のひとつがこの校閲作業にあります。おっと。そろそろ新作の初校が仕上がって来る頃合いかと。








