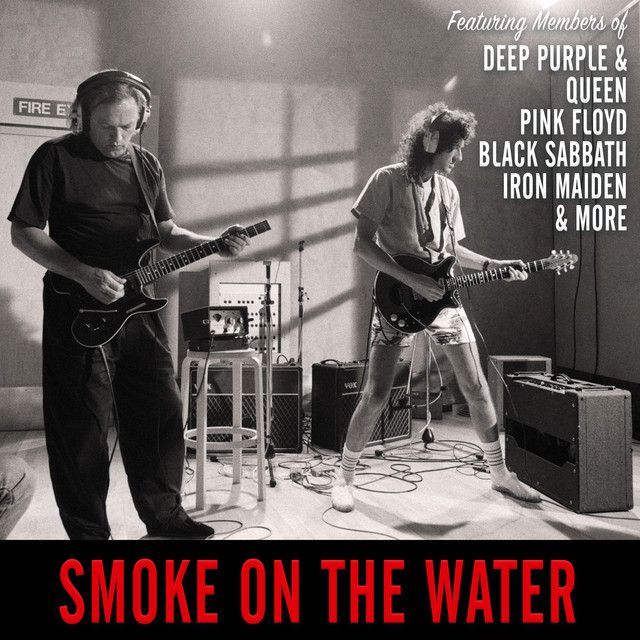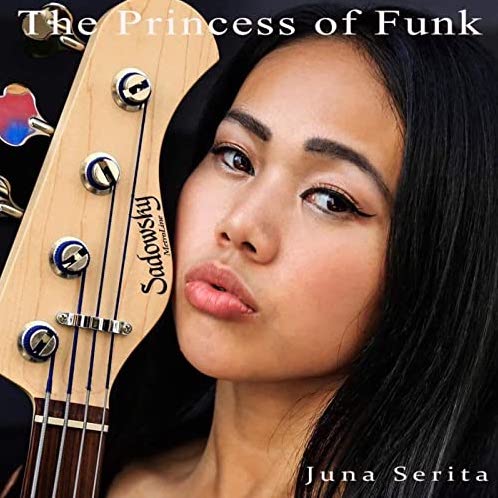先月30日、東京ガーデンシアター (東京・有明) で催された安全地帯のデビュー40周年記念アニバーサリー・コンサート『安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT “Just Keep Going!” Tokyo Garden Theater -4 Days-』の最終日を鑑賞して来ました。
1982年(昭和57年) にデビューを果たし、翌年リリースした『ワインレッドの心』の大ヒットでスターダムに駆け上がった安全地帯はある意味、バブル経済絶頂期を象徴するロックバンドのひとつと云えるでしょう。
当時、米国留学を終えたばかりの私は、濃い目のファンク・ミュージックや泥臭いサザン・ロックに心酔していたため、この国の”軽め”のロックとやらには殆ど興味がありませんでした。女性から「素敵だから聴いてみて」と安全地帯のカセットテープを渡されても、そもそも流行のテクノカットというものが気に入らず、そのまま放っておいた記憶があります。
そんな未熟な私が、リーダーである玉置浩二さんのメロディ・メーカーとしての天賦の才に気づいたのは、彼がソロになってからのこと。遡って彼が世に送り出した作品の数々を聴き返し、遅まきながら玉置さんが日本における最高のロック・シンガーであることを思い知るに至ります。今回、安全地帯のコンサートに初めて接する機会を得て、30数年を経て私は改めて安全地帯を、そしてあの「時代」を再認識することとなりました。
未曾有のバブル経済成長期は、社会構造のみならず人々のメンタリティにも多大な影響を及ぼしました。特に東京では、日増しに疾走感が増し、銀座、六本木、新宿…。街には熱気が充満し、社会全体が爛熟して行った。そんな様子を、まるで昨日の出来事のように想い出します。地価は見る見るうちに上昇し、企業は次々と最高益を叩き出す。人々は「時代」と並走することを選び、昂揚し、狂騒し、そして「明日は必ず今日よりも豊かになれる」と信じ、一心不乱に踊り続けました。
それでも実際には、「時代」に恋をしている女性たちばかりではありませんでした。愛せなかった女性たちも確実にいた。それは、お嬢様ファッションに身を包んだ楚々とした女性たちばかりではなく、膝上20センチ丈の超ミニスリップドレスを”戦闘服”と称し、”お立ち台”でジュリ扇を振りかざしていたトサカ前髪の女性たちとて同じでした。ミラーボールの下で、歪んだ笑みを不器用に作って見せた女性たちがいたことを、今でもはっきりと覚えています。しかしながら、ドンペリピンクの泡沫に溺れ、心地良い不感症と戯れていた私は、そうした女心の機微に気づく術も繊細さも持ち合わせてはいなかった。
「時代」のスピード感にとまどい、「時代」と添い寝したくとも出来ずに立ち尽くす。「ねぇ、私を見て、真っ直ぐに見詰めて」。そこには、無慈悲な「時代」に置き去りにされた「純愛」がありました。焦躁に駆られ、逡巡する女性たちに、安全地帯は優しく語りかけます。
『悲しみにさよなら』(作詞 松井五郎 作曲 玉置浩二)
〽 泣かないでひとりで ほゝえんでみつめて
あなたのそばにいるから
悲しみにさよなら ほゝえんでさよなら
ひとりじゃないさ
玉置さんが紡ぎ出した珠玉の旋律は、ひとりぼっちの彼女たちの、揺れる心と同期する周波数を確かに備えていた。「君は、君のままでいいんだよ」。「時代」が異常なのであって、あなたの「世界」は決して侵されるべきじゃない。まさに彼らの作品は、狂乱の時代において、彼女たちの「安全地帯」となっていました。
切ないラブ・バラードを熱唱する玉置さん。超満員の客席で静かに揺れるスマートフォンのペンライト。なぜか、ステージがぼやけて見えた。それは、甘ったるいノスタルジーなどではなく、「時代」と節操なく”交尾”したあの頃の自分自身に対する悔恨の念だったのかも知れません。