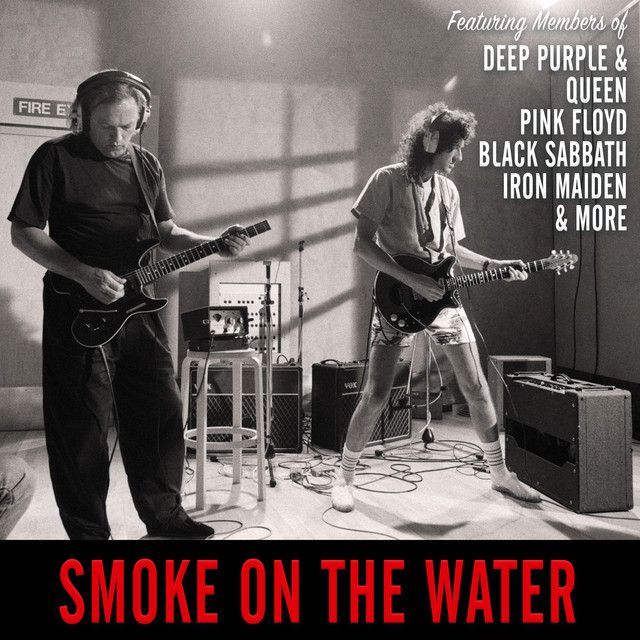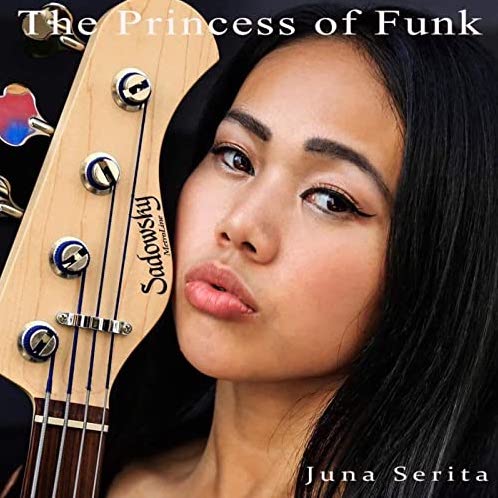先月9日まで東京都美術館 (東京・上野) で開催されていた『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』を鑑賞しました。エゴン・シーレとの出会いは、高校生の頃。心臓壁をギリギリと切り刻むような凶暴極まりない筆致、そして「性」への執着を包み隠すことなく曝け出す淫らな色彩に魅せられ、瞬く間に虜となりました。以降、シーレは彫刻家アルベルト・ジャコメッティと並んで、私が最も敬愛するアーティストであり続けています。
彼の作品に初めて邂逅したのは1986年 (昭和61年) 、ニューヨーク近代美術館 (MOMA) で開催されていた『Vienna 1900: Art, Architecture & Design』 展でした。この大規模な回顧展が、シーレやグスタフ・クリムト、オスカー・ココシュカらいわゆるウィーン分離派 (Wiener Secession, Sezession) を世界の美術界が本格的に”再評価”するきっかけとなりました (55年に独ヘッセン州カッセルで開催された現代美術展第1回『ドクメンタ』や62年にミュンヘンの「ハウス・デア・クンスト」[Haus der Kunst]で開かれた展覧会がその嚆矢とされています)。同年、実家にほど近い神奈川県立近代美術館で催された『エゴン・シーレとウィーン世紀末』展 (EGON SCHIELE UND WIEN ZUR JAHRHUNDERTWENDE) にも幾度となく通い、シーレの”狂気”に心酔するに至りました。

「またシーレと会える」。今回の企画展を心待ちにしていた私が、これまで同展について言及しなかった理由は明白です。結論から云えば、極めてレベルの低いキュレーションに失望したからに他なりません。まずもって『エゴン・シーレ展』といったタイトルに偽りアリでした。同展には確かに約50点の作品が出展されてはいましたが、代表作と呼べる作品は数点に留まり、シーレの鮮烈な画業を総覧するだけの厚みはありませんでした。これでは彼の”狂気”の一端に触れるどころか、新たなファンを獲得することさえ難しかったでしょう。
かと云って37年前の企画展同様、オーストリア=ハンガリー帝国〜第一帝国 (現・オーストリア共和国) の古色蒼然とした芸術家団体クンスラーハウス (Künstlerhaus) に反旗を翻し、「伝統」からの「分離」を目指した総合芸術ムーブメント「ウィーン分離派」に焦点を当てるにしてはボリュームが圧倒的に足らない (クリムトの作品はデッサン1枚のみ)。要は今の時代に、シーレの研ぎ澄まされた刃をどこに突き刺すための展示だったのか? 毒もなければヴィジョンも乏しい中途半端な展示に終始していました。
オーストリア共和国ウィーンにあるレオポルド美術館は、ルドルフ・レオポルド夫妻によって収集された5,000点を超えるウィーン分離派の個人コレクションを所蔵する同国を代表する美術館です (2001年開館)。
1925年 (大正14年) にウィーンで生を受けたルドルフは、ユダヤ人であったがために国家社会主義ドイツ労働者党 (ナチス・ドイツ) から身を隠す生活を余儀なくされます。戦後、50年代になって彼は、まだ安値で取引されていたウィーン分離派の収集を始めました。シーレの作品が当時、表舞台から遠ざかっていた(遠ざけられていた) 理由は、ナチス・ドイツの台頭と密接な関係があります。

ハンガリー出身でユダヤ人でもあった哲学者マックス・ノルダウは、その著書『退廃』(Die Entartung) の中で、近代芸術は隔世遺伝的な退廃に冒された劣等な人々によって作られていると喝破しました (1892年)。この退廃芸術 (Entartete Kunst ) 批判は、アーリア民族の優位性を賛美していたナチス・ドイツに悉く利用され、ユダヤ人やコミンテルンの”文化ボリシュヴィズム”の手先とされた芸術家の排斥運動へと繋がり、国内20ヶ所以上の美術館から押収された作品は1937年にミュンヘンで開催された『退廃芸術展』において意図的に晒し者にされます (4年間かけてドイツ国内の13都市を巡回)。
同展にはマルク・シャガールやマックス・エルンストの作品も含まれていましたが、17年にすでに死没していたシーレもその影響を免れることは出来ませんでした。”猥褻”の烙印を押された彼の作品はナチス・ドイツによって没収され、散逸していたため作品が返還されるまでには紆余曲折を経ることとなります。
1938年にドイツ国によって併合、アンシュルス (Anschluß; Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich) されたオーストリア国民は、「大ドイツ主義」(Großdeutsche Lösung) にあっては”二流市民”と見做されたため、その”汚名”をそそぐべくホロコーストにも積極的に加担しました。”退廃芸術”に対する迫害も同じくで、大戦終結後も戦争責任については長らくタブー視されていたことが、シーレを始めとするウィーン分離派の”再評価”が遅れた最大の原因となりました。
自由な表現の象徴である芸術領域への政治介入は、決して珍しいことではありません。特に、一般大衆の関心が集まりやすい”猥褻な図画”がまずは槍玉に上がり、摘発・排斥の対象となります。芸術と云えども時代と遊離しては存在し得ません。”性”と真正面から向き合ったシーレの作品こそ、セクシュアリティの境界線が曖昧な今の時代に鋭利な切っ先を向けられたはずです。我が国のアート界に圧倒的に欠落しているのは、こうした身心が軋むような”狂気”であることを改めて実感させられた無粋につるりとした『エゴン・シーレ展』でした。