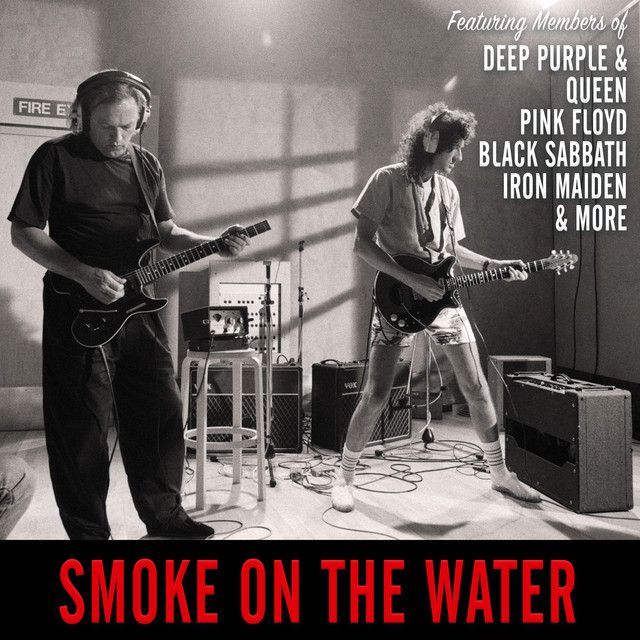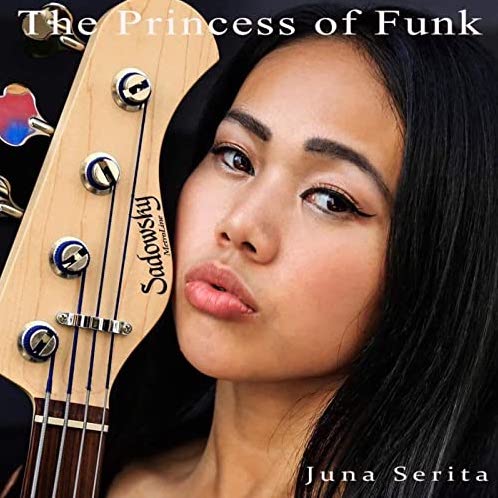大谷石の石塀に、点々と黒染みが浮かぶ。いくら洗浄しても、表層を削ってみたところで、取り除けないどころか逆に、経年によって黴ついたどす黒い内部がみしりと顔を覗かせる。”戦争の記憶”とは、そのようなもの。兵隊として戦場に赴いた者、戦火に巻き込まれた無垢の住民のみならず、兵隊たちを送り出した者たちにも決して消し去ることの出来ない疵を残す。
先週、鑑賞させて頂いた秋田雨雀・土方与志記念 青年劇場の瓜生正美追悼公演 第一弾『殺意』 (原作 飯尾憲士、構成・脚本 瓜生正美、演出 シライケイタ) にも、そうした”残された者たち”のこの世の地獄が描かれていました (東京・新宿 青年劇場スタジオ結にて今月18日まで)。
1964年(昭和39年) に7名の仲間たちと同・劇団を起ち上げた瓜生正美氏がこの芝居をしたためたのは96年(平成8年)。戦後半世紀を経て、辛うじて戦争体験者がまだいた時代のことです。主人公の花井トメは、借金のもつれから出刃包丁で若い男に怪我を負わせ、殺人未遂罪に問われます。70歳を過ぎた物静かな老婆がなぜ?
相手は、大日本帝国陸軍によって兵隊に取られ、いじめや体罰に会って自ら命を絶った息子の戦友 谷口鉄三。「お金は、どぎゃんこつあってもはろうてもらわにゃならんとです」。堰を切ったかのように鬼の形相で鉄三に迫るトメ。金が欲しいわけではない、国を恨んだわけでも、鉄三を憎んだわけでもない。得体の知れないドロドロとした不条理な哀しみが、小柄なトメの肉体から止めどなく噴き出します。それは、トメの心にザックリと刻み込まれた”戦争の刻印”だったのかも知れません。

青年劇場の元・代表で劇作・演出家だった故・瓜生正美氏
私の幼少期には、両親を始め周囲にまだ戦争体験者がいらっしゃいました。知人宅を訪問し、仏壇に手を合わせる。ご子息が早逝されていれば、「戦争に行かれたのですか?」といった会話が何の違和感もなく交わされていた時代です。
瓜生正美氏は、東京帝国大学 (現・東京大学) 在学中に学徒出陣し、長崎への原爆投下翌日には遺体処理や被災者の救護に駆り出されて入市被爆するといった壮絶な経験をされています。「時が、疵を癒やすのか?」。終生、戦争を描くことにこだわった瓜生正美氏が世に、そして自分自身に問うたのは、この一点だったのではないでしょうか。
戦争を知らぬ者は、理屈や抽象論で戦争の「悪」を糾弾する。まるで鬼の首を取ったかのようにしたり顔で「正義」とやらを語って見せる。しかし、そこではない。大切なのは、そこではないのだ、と彼は云っているように、私には思えてなりません。「憎悪」や「憤怒」だけでは言い表せない沈殿した想い、言葉では表現出来ない感情の崩壊が、『殺意』にも顔を覗かせます。その顔には、目も鼻も口もない。唯々、ぽっかりと空いた真っ暗な穴があるだけ。そこに死神は、いつまでも、いつまでも潜んで、手招きをしています。
上演後には、唐十郎氏の『劇団 状況劇場』や鈴木忠志氏の『劇団 早稲田小劇場』に出演し、故・寺山修司氏や野田秀樹氏とも交流があった演出家でアングラ演劇界を代表する俳優でもある流山児祥氏の大変興味深いアフタートークもあり、殊の外、充実した一夜となりました。劇団員の皆様、お疲れ様でした。