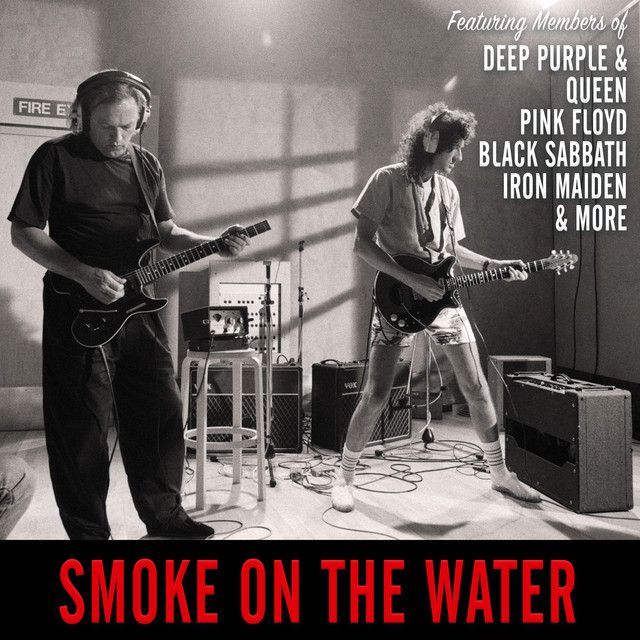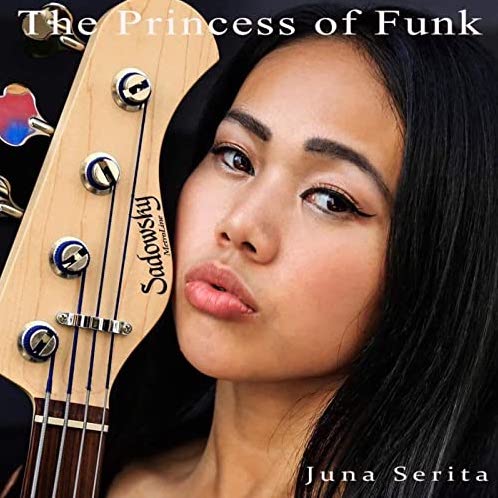今月発売されたチャールズ・ペレグリーノ氏の新著『Ghosts of Hiroshima』の表紙
米映画『タイタニック』や『ターミネーター』、『アバター』といった数々のメガヒット作で知られるハリウッド映画界の巨匠ジェームズ・キャメロン監督が愈々、”原子爆弾”をテーマに据えた新作の製作に着手したと報じられています。
米『ローリング・ストーンズ』誌のロング・インタビューに応じた同監督は (今月5日付)、映画化権を購入したチャールズ・ペレグリーノ氏の新著『Ghosts of Hiroshima』 (邦題: ゴースト・オブ・ヒロシマ) を下敷きに、広島と長崎で被爆した”二重被爆者”故・山口彊氏を主人公に据えたヒューマンドラマを製作すると語っています。ちなみに私の友人であるアリ・ビーザーとの共著『「キノコ雲」の上と下の物語〜孫たちの葛藤と軌跡』 (朝日新聞出版) を上梓された原田小鈴さんは山口氏の孫娘にあたります。
同監督が核兵器に興味を抱いたきっかけはキューバ危機 (1962年) でした。当時8歳であったカナダ出身の彼はその時、「世界はそれまで自分が考えていた世界とはどうやら違うようだ」と気づきます。高校生になって出会ったジョン・ハーシーの著書『HIROSHIMA』 (邦題: 『ヒロシマ』) に衝撃を受け、核兵器の構造や核分裂反応の物理的作用とその効果について自ら学習し、そこで得た世界観が後に『ターミネーター』や『ターミネーター 2』に繋がったと云います。
そのため「核兵器は私の人生の一部であり、愈々それと向き合う時が来た。それもフィクションであったりSFではなく、事実に基づいた作品でなければならない」。つまり”原子爆弾”は71歳を迎えた彼にとって、単なる映画の素材ではなく、彼自身の原点であることが判ります。
キャメロン監督は、2009年 (平成21年) 12月22日にペレグリーノ氏と共に長崎市内の病室で実際に山口氏と対面しています。彼が亡くなる2週間ほど前のことです。山口氏はすでにげっそりと痩せ衰えておられましたが、キャメロン監督は「私は彼の中に、彼が生き続ける理由を垣間見たような気がしました。それはバトンを誰かに渡したい、といった情熱でした」と述懐しています。
「人生の終末が近づくにつれ、彼は精神的に聖人の境地に達していましたが、何よりも彼は核兵器によって家族や友人、地域社会が苦しむのは金輪際見たくない。二度とあのようなことが起こならないように阻止しなければならない。非難と憎悪、そしてトラウマの連鎖を断ち切らなければならないと訴えていたように思います」。山口氏からバトンを手渡された。
「1945年8月6日は、人類がルビコン川を渡った日」と古代ローマにおける禁断の進撃に例えて米軍による原爆投下を指弾する同監督は、「何があろうとヒューマニティを最も尊重しなければならない。そうでなければただ殺し合ったり、核兵器で攻撃したり、何らかの形で相手を罰することを正当化してしまうことになる。これは私たち人類にとって壮大な挑戦です。私が映画監督として、この物語を伝える媒介者になれるレベルにまで進化しようと自分自身に挑戦を課しているのと同じように。うまくやり遂げられるかどうかはわからないけれども、これがどれほど困難な作業であるかを承知の上で挑戦してみたい」と、新作に対する心構えを語っています。
「あなたほどの名監督が自信がないと云うのは意外です」と問いかけるインタビュアーに対して彼は、「私がSFX (特撮技術) を駆使して完璧に作り上げれば、最初の20分間ですべての観客が恐怖心から劇場を後にする類の作品を作ることは可能でしょう。ただ、それが私の目的ではない。私が成すべきことは、山口氏を始めとする被爆者が直面せざるを得なかった現実に観客を引き込み、共感を呼び起こす。日本語には”おもいやり”という美しい言葉がありますが、ただ共感したり同情するだけではなく挑戦する。観て下さった方々が起ち上がって何かをやる、やらなければならないと心から思わせる。そういった要素を組み込みたい。精神的な進化は必ず起こるべきだと考えています。もしも私たちが真剣に核兵器をなくすつもりなら、それは人々が『もうたくさんだ、この狂気を止めなければならない』と声を上げることからしか生まれない」。
これは私がパティ・スミスさんから伺った認識と同じです。まずは事実を知ること。そして声を上げ、連帯する。そのためには音楽や映画、絵画といったアート・フォームが強力な”武器”となり得ます。

故・山口彊氏。2010年 (平成22年) 1月4日に93歳で逝去
この記事を通じて、キャメロン監督の本気度がひしひしと伝わって来ました。私はクリストファー・ノーラン監督がメガホンを取り、作品賞など米アカデミー賞最多の7冠に輝いた『Oppenheimer』 (邦題: オッペンハイマー) の映画評で「おそらくは 『オッペンハイマー』 ”以前”と”以降”に区分けされ、”核”を語る上では欠かすことの出来ない非常に”危険”な作品となることでしょう」と綴りました(https://www.japanews.co.jp/concrete5/index.php/Masazumi-Yugari-Official-Blog/2024-06/隠蔽の世紀を超えて)。同作は人類初の原子爆弾を開発し”原爆の父”と称された理論物理学者J・ロバート・オッペンハイマー博士の伝記映画でしたが、キャメロン監督の視座は異なります。彼の言動からは、ヒューマニズムによって悪魔の兵器を無力化しようとする意図が強く感じられました。
「山口さんのストーリー以外にも、人々が互いに助け合ったといったエピソードは数多く残されています。彼らはおそらく死に瀕していた、死を覚悟していたでしょう。それでも互いに助け合った。これはおそらく非常に日本的な精神性でしょう。私は日本人ではありませんが、こうした文化的な側面にまで深く入り込まなければならない。彼らの視点からストーリーを語ることは少し押し付けがましい気もしますが、そんなことはどうでもいいのです。誰かがこの事実を語らなければならない。私は愛国主義、国家主義的な米国の視点から語るつもりはまったくありません。私はあくまでも映画作家であり、社会政治的な側面に関わるつもりもない」 (著者注: キャメロン監督は、興行的に芳しくない作品となることも受け入れる心の準備が出来ているようです)。
インタビューの最後に、彼は改めて決意のほどを語っています。「原爆投下は人類が犯した最悪の行為です。映画監督として作品化する以上、どうして非難せずにいられるでしょう? 爆弾投下を描くには、ある種の批判がつきものです。ただ、伝えるべきメッセージは、『これは実際に起こった。生身の人間の上に起こった』ということであり、なぜ起こったのか、誰が悪いのかといったことではない。原爆投下は琥珀の中に閉じ込められた歴史の瞬間であり、私たちはそこから学ばなければならない。なぜならばその”記憶”こそが、私たちが生き続ける”解”となるかも知れないからです」。
80年間にもわたり政治的理由によって封印され続けて来た被爆の実相が、原爆を投下した米国の映画人の手によって今、明らかにされようとしています。エンターテインメントの真髄を究めたキャメロン監督の手による”原爆映画”は、確実に世界中の人々の関心を呼び起こし、大きな反響を生むこととなるでしょう。潮は確実に変わりつつあります。為政者ではなく、アーティストの力によって核兵器は確実に廃絶の道を歩み始めようとしています。
被爆地・広島、長崎は、被爆国・日本は、こうした時代の大きな転換期にどのように対峙するのでしょうか。ノーベル平和賞受賞と同じく唯々、降って湧いた”幸運”に有り難うございました、と感謝の意を表するだけでしょうか。それとも自らの力でさらに核廃絶の動きを押し進めるべく身体を張るのか。世界は、私たちがいかに行動し、発言するかをじっと見詰めています。今こそ私たちのモラルと覚悟が問われています。