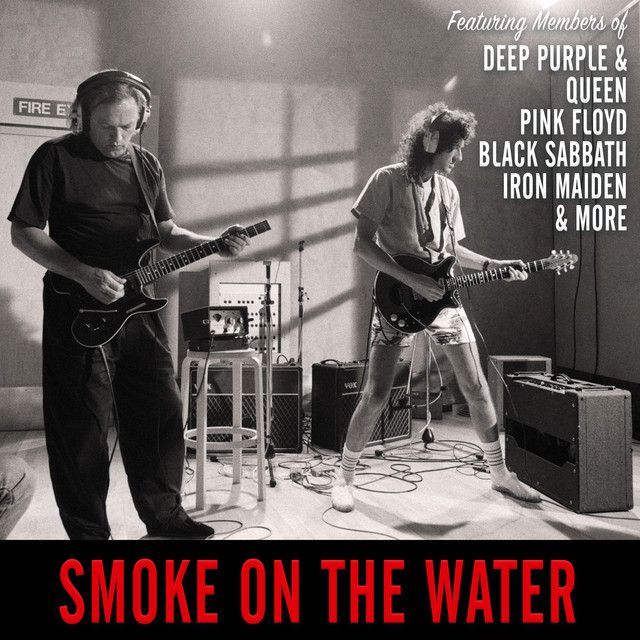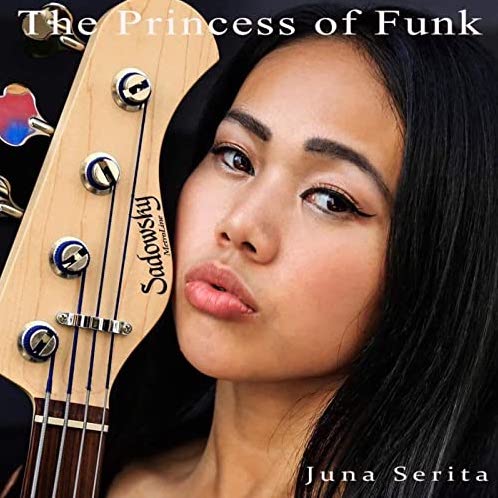東京国立近代美術館 (東京・北の丸公園) で開催中の『コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ』を鑑賞しました (今月26日まで)。
私はこれまで、体験者 (被爆者) のみが有する「記憶」を、今を生きる若者たちが「記録」する芸術活動を広く告知・啓蒙することで、いかにして忘れてはならない過去の歴史を次世代へ、世界へ継承するかを熟考し、行動し、実践して来ました。他方、本展はこれとは逆のベクトルで、絵画や写真といった視覚的表現を用いた「記録」がどのように国民の「記憶」に影響を与え、再構築したかを美術館という記憶装置において考察する極めて挑戦的かつ意義深い内容でした。
さしたるヴィジョンを持ち合わせていないにも関わらず、安易に”戦後80年”を騙る企画展もある中、本展は学芸員 (キュレーター) の見識と覚悟が際立った見事な展示構成となっていました。
本展は、同館が収蔵する戦意高揚と戦争を記録する目的で描かれた”戦争記録画”を軸に、他機関所蔵の作品・資料も加え、我が国がアジア・太平洋戦争に突入して行った1930年代から、戦争の「記憶」を題材に据えた1970年代の作品に至るまでを重層的に網羅。”美術”がいかに戦争に加担し、流通し、消費されたかをつぶさに追体験出来る設えとなっていました。
それにも関わらず、タイトルに「戦争」の二文字がない。そこからは定型化した政治的解釈に囚われることなく、”戦争記録画”を芸術史の文脈の中で客観的に捉え、その戦争責任の在り方を改めて問う前例のない”空間”を生み出そうと尽力した学芸員の熱意と苦悩の跡を読み取ることが出来ました。
各章には「絵画は何を伝えたか」、「アジアへの/からのまなざし」、「戦場のスペクタル」、「神話の生成」、「日常生活の中の戦争」、「身体の記憶」、「よみがえる過去との対話」、「記録をひらく」といった象徴的なタイトルが架せられ、絵画のみならず当時のポスターやグラフ誌、漫画も併せて展示することで「尽忠報国」の精神を国民に刷り込んだ視覚的表現・効果の実態を明らかにして行きます。向井潤吉はバターン死の行進で知られる米軍捕虜の様子を描き (『四月九日の記録 (バタアン半島総攻撃)』1942年)、中村研一はマレー半島北端のコタ・バルにおける上陸作戦で海岸線を匍匐前進する兵士たちを活写しました(『コタ・バル』1942年)。
アリューシャン列島のアッツ島において米第7歩兵師団の攻撃によって全滅した山崎保代陸軍大佐率いる守備隊を描いた藤田嗣治の『アッツ島玉砕』 (1943年)。本展においても藤田と小磯良平の画力が抜きん出ていたことが判ります。
戦時中、多くの芸術家たちが帝国陸海軍によってプロパガンダの創出に駆り出されました。大東亜共栄圏の理想に共鳴した者、生活を支えるために”心を売った”者など、その理由は様々でした。その代表格として挙げられるのが藤田嗣治です。1913年 (大正2年) に渡仏し、エコール・ド・パリのパブロ・ピカソやアメデオ・モディリアーニらと親交を深め、時代の寵児となった藤田でしたが、33年 (昭和8年) に帰国。アジア・太平洋戦争中は陸軍美術協会理事長として積極的に戦争画を描き、「遂げよ 聖戦 興せよ 東亜」の精神を具現化して行きます。本展にも『シンガポール最後の日 (プキ・テマ高地)』 (42年) や『アッツ島玉砕』 (43年) など4点の作品が出展されていますが、細部に目を凝らすと”戦争記録画”といった型通りの枠に留まることなく、戦闘の残虐性をも精緻に描写していることに衝撃を覚えます。
しかしながら「玉砕」という文言はやがて軍部によって美化され、国に殉じる行為が帝国軍人の鑑と讃えられたことから、同年9月に開催された『国民総力決戦美術展』においては作品の前に賽銭箱が置かれ、脇に立った藤田が、観客が賽銭する度にお辞儀をして見せたとも伝えられています (『四百字のデッサン』野見山暁治 著)。藤田自身も「そのアッツ玉砕の図の前に膝まづいて両手を合わせて祈り拝んでいる老男女の姿を見て、生まれて初めて自分の画がこれ程迄に感銘を与え拝まれたと言ふ事はまだかつてない異例に驚き、しかも老人達は御賽銭を画前に投げてその画中の人に供養を捧げて瞑目して居た有様を見て、一人唖然として打たれた」と自ら巡回展で目撃した光景を述懐しています (『藤田嗣治芸術試論―藤田嗣治直話』夏堀全弘 著)。こうしたエピソードからも判るように、優れた芸術作品は作家の手を離れると同時に時代に、権力者の思惑・要請によって”武器”へと姿を変える危険性を常に孕んでいます。
絵画的に私が最も魅せられた鶴田吾郎の作品『神兵パレンバンに降下す』 (1942年)。
一方で本展では、「身体の記憶」と題された6章では丸木位里・俊が描いた『原爆の図 第2部 火』と『原爆の図 第3部 水』 (いずれも再制作版。広島現代美術館 所蔵) が展示され、7章「よみがえる過去との対話」では広島平和記念資料館が所蔵する被爆者が自ら描いた「原爆の絵」15点も紹介されています。いかにアーティストが、市井の人々が”芸術”というフィルターを通じて過去と向き合い、国粋主義的思想の復活に抗ったか、平和を希求したか。その道程をも併せて俯瞰することで平和の意味を改めて考える足がかりを与えてくれます。
“戦後80年”を経て我々は再び、「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境」といった根拠が極めて脆弱な妄言に籠絡され、浮き足立っています。SNS上ではAI (人工知能) を駆使した反知性主義が氾濫してもいます。こうした”茫洋たる不安感”が蔓延する今であるからこそ、「記録をひらき 記憶をつむぐ」ことに意義があります。表層をなぞるだけではなく明確な構想と意識を持った学芸員が真摯に取り組んだ本展は、必ずや後世に語り継がれる展示となるでしょう。芸術の要諦とは、そういうことです。