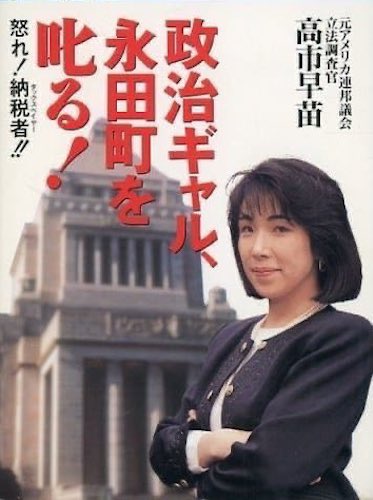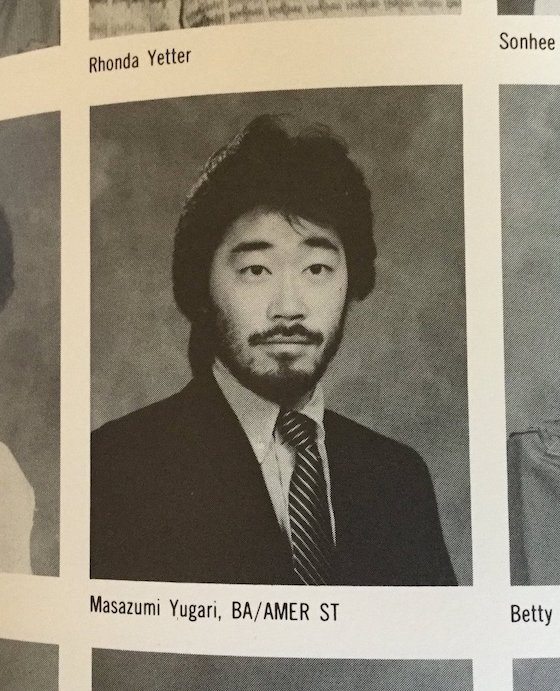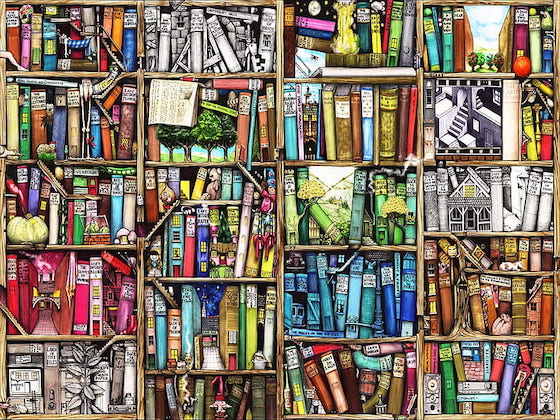米ニュースメディア『POLITICO』 昨年11月21-27日号
3年前の昨日、ロシア連邦によるウクライナへの全面侵攻が始まりました (クリミア半島への侵攻は2014年3月1日から)。両国間の戦闘は、なぜこれほどまで長引いたのか。歴史的、経済的、地政学的理由は幾つもありますが、ひとつには北大西洋条約機構 (NATO) の集団防衛体制の再編、危機管理能力のアップグレードがその背景にあったことは明白です。
NATO加盟国はウクライナ侵攻後、毎年400億ユーロ (約7兆円) の軍事支援を続けて来ました。一方、米国はジョー・バイデン前政権時代に議会が承認した5回の支援金額の合計は1,830億ドル (約27兆円) にも上りますがその内、約700億ドル (約10兆円) は米国内における武器生産に充てられたためウクライナへの直接支援はNATOを下回っています。
そもそもウクライナは、1991年 (平成3年) に旧・ソビエト社会主義共和国連邦 (旧・ソ連) から独立を果たすまでは旧・ソ連の構成共和国のひとつでした。そのためウクライナ軍は旧・ソ連製兵器を装備し、かつては大陸間弾道ミサイル (ICBM) 176基分1240発の核弾頭も保有していました (米露間の戦略核兵器削減条約START 1の発効に伴い96年6月にロシア連邦への移送完了)。
今回の戦闘によってこれら旧式の旧・ソ連製兵器は速やかに”消費”され、かつて友好協力相互援助条約機構 (ワルシャワ条約機構) に加盟していたポーランド共和国 (旧・ポーランド人民共和国 ) やハンガリー共和国 (旧・ハンガリー人民共和国) といった国々も、長年保有していた旧・ソ連製兵器をこぞってウクライナへ供与しました。云ってみれば、今回のウクライナにおける戦闘は、現在はNATOに加盟している旧・東側諸国にとって、旧・ソ連製兵器の”在庫一掃セール”でもあったわけです。
こうして”空になった兵器庫”を各国は、米国を始めとする旧・西側諸国製の兵器と入れ換えることで補填(但し、その殆どが価格のこなれた旧式兵器)。まさにドミノ現象よろしく、この短期間で欧州の勢力図はNATO色に染められました。軍需産業が活況を呈した理由はそこにあります。

多用途戦闘機 F-16 ファンディング・ファルコン。現在でも4,600機以上が世界各国で運用されている名機。航空自衛隊は、この機体をベースに日米共同改造開発したF-2A/Bを98機配備しています。
旧・ソ連製兵器と米国製とではスペックから操作方法に至るまで、まったく異なると云って良いでしょう。そのためNATOに加盟している国同士であっても軍事能力格差が著しく、これまで統一指揮下で相互運用することは容易ではありませんでした。それが今回の軍事侵攻によって旧・西側製の兵器に統一されたことから、皮肉なことにも迅速かつ緊密に共同作戦行動が取れる環境が整いました。つまり、昨年3月のスウェーデン王国とフィンランド共和国 (23年) のNATO加盟により、NATOにとっての悲願は昨春の段階ですでに達成されていたことになります。
しかしながら、軍事知識が乏しければ理解し辛いところですが、兵器というものは手にすればすぐに使えるというわけではありません。例えて云えば、トヨタ セリカ1600GTでは”サーキットの狼”と呼ばれていても、ポルシェ992を乗りこなせるとは限らない。ウクライナが切望していた多用途戦闘機 F-16 ファイティング・ファルコンの供与を米国が漸く決定したのが23年5月。同年8月にはデンマーク王国 (19機) とオランダ王国 (24機) が正式に供与を表明し、昨年8月に実戦配備されています (その他ベルギー王国 30機、ノルウェー王国 22機)。とは云え、旧・ソ連戦闘機に習熟していたパイロットであっても、F-16の操縦技術を身に付けるまでに1年近くの時間を要しました。
ちなみにデンマークが供与したのは赤外線誘導のAIM-9サイドワインダー空対空ミサイルやレーダー誘導のAIM-120 AMRAAM (アムラーム) 空対空ミサイル等を搭載した 近代化型 (MLU) のF-16AM/BMでした。F-16自体は78年 (昭和53年) に運行開始された第4世代の戦闘機ですが、これだけの装備が施されれば最新鋭機と比較しても遜色のない攻撃・防衛能力を有しているため、両国間の戦闘は新たなステージを迎えることとなりました。
米国がF-16の供与を渋った理由は、前述の通り旧式兵器の”消費”が一巡し、当初目標はすでに達成されていたからに他なりません。それに加えて今後、ウクライナが旧式ではなく最新鋭の武器を用いてロシア領内に侵入し、対地攻撃に歩を進めれば、更なる戦闘の激化・拡大は避けられない。現在、米露間で停戦交渉が迅速に進められているのも、他国を巻き込んだ戦争拡大のリスク、逆ドミノ現象を避けるためと云えるでしょう。
ウクライナ人の想いを他所に、停戦交渉は米露間で粛々と進められています。ウクライナの国民的詩人タラス・シェフチェンコはその詩篇『ザポビット』で、地政学的要衝に位置する祖国の哀しみを切々と詠っています。
わたしが死んだら
葬ってほしい
なつかしいウクライナの
ひろびろとしたステップに抱かれた
高い塚の上に
はてしない野のつらなり
ドニエプルも
切り立つ崖も
見わたせるように
哮り立つとどろきが
聞こえるように
ドニエプルの流れが
ウクライナから 敵の血を
青い海へと 流し去ったら
そのときこそ 野も山も…
(訳 藤井悦子)