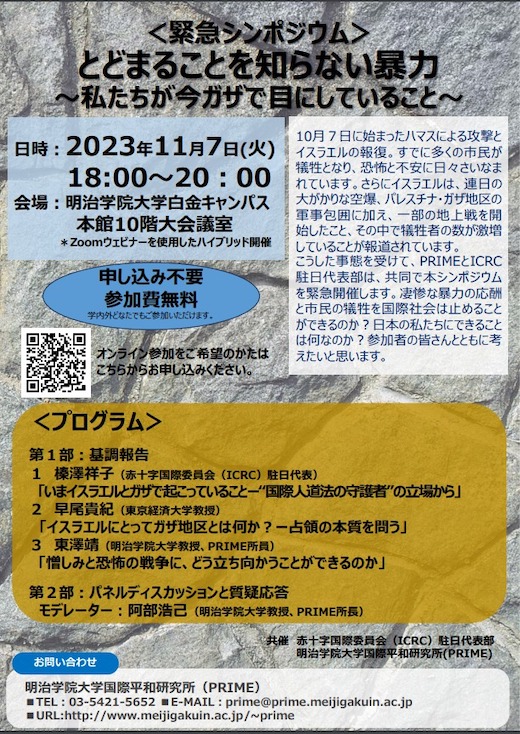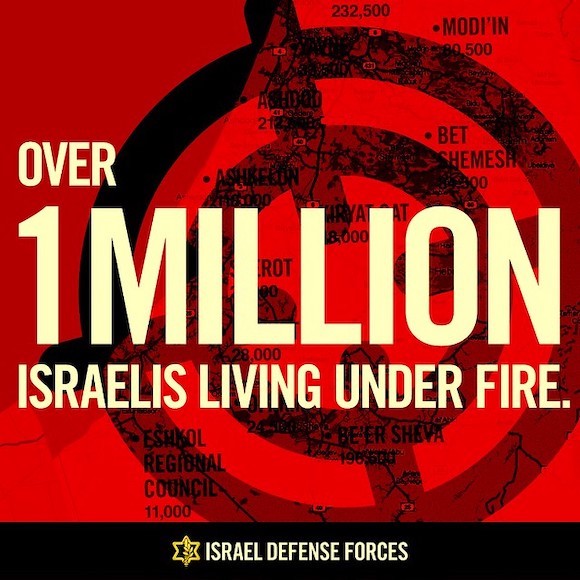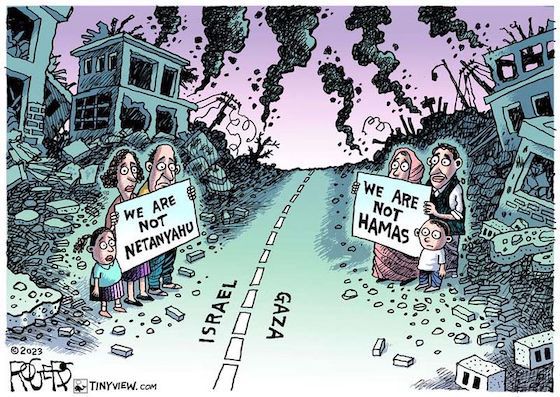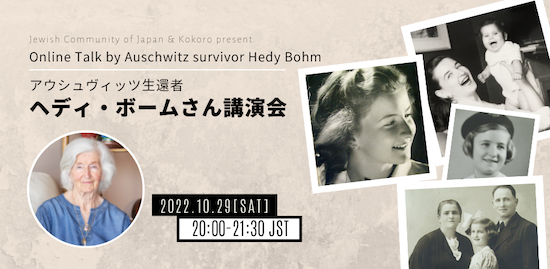昨今のコメの価格高騰を受け、大手流通グループ イオンが米カリフォルニア産のカルローズ米 (Calrose) 「かろやか」の販売を来月から順次開始すると報じられています。カリフォルニア米と云えば、忘れてはならないのが国府田敬三郎。彼の地で水稲の大規模生産技術を確立し、”ライス・キング”の異名を取った立志伝中の人物です。
私が米国に留学していた当時、特に東海岸に位置するフィラデルフィアでは国産米を入手することは極めて困難で、中華街まで足を運んで「國寶ローズ」 (Kokuho Rose) を買い求めていました。このカリフォルニア米は中粒種のカルローズで、国産米よりは軽い食感でもちもち感も少ないため、どちらかと云えばチャーハンやリゾットといった洋食との相性が良い品種でした。それでもなぜか炊飯器は使わず、飯盒炊爨よろしく鍋でグツグツと白米を炊いていた貧乏学生時代が懐かしく想い出されます。
「國寶ローズ」の産みの親 国府田敬三郎は福島県磐城郡の出身で (現在のいわき市北部)、福島県師範学校 (現・福島大学) に進学したものの米国への憧れが捨て切れず、25歳の時に単身渡米。1920年 (大正9年) に1,800エーカーの土地を借り入れて米作を始め、世界恐慌や太平洋戦争といった様々な困難に見舞われながらも、飛行機で水田の播種を行うなど斬新な手法を駆使し、カリフォルニアの地に米作を根付かせました。
米国における稲作は、17世紀にサウスカロライナ州で始まり、ジョージア州やルイジアナ州といった南部一帯に広まりました。19世紀半ばには、ゴールドラッシュによってカリフォルニア州に流入した約4万人の中国人労働者の胃袋を満たすべく米作が発展。日本を除くアジアで広く栽培されている長粒種 (インディカ米) が当時は主流でしたが、ジャポニカ米を定着させ、いわゆるカリフォルニア米を完成させたのが敬三郎率いる国府田農場でした。

国府田敬三郎 (1930年頃)
覚えている読者もいらっしゃるでしょうが、93年 (平成5年) に我が国は記録的冷夏により深刻な米不足に陥りました。政府備蓄米をすべて放出しても約200万トンが不足したため細川内閣 (当時) はタイ王国や中華人民共和国、米国から計259万トンの緊急輸入を行い、それまでの国是であった「コメは一粒たりとも輸入させない」といったコメの全面輸入禁止政策に大転換をもたらしました。
こうした非常事態を受けて、私は米誌『ニューズウィーク』のアサイメントでコメの輸出大国であるタイ王国とベトナム社会主義共和国に赴き、現地の大手米卸売業者や流通ルートを取材し、”世界の米事情”を明らかにしました。国策によってコメは保護されていただけに、当時の日本人はコメの国際取引市場に関する知識はまったくと云って良いほど持ち合わせていなかった時代です。
折悪く、関税及び貿易に関する一般協定 (GATT) のウルグアイ・ラウンドを交渉中であった日本政府はミニマム・アクセスを受け入れ、コメの貿易自由化をスタートせざるを得なくなります。加えて99年 (平成11年) にはコメの関税化へと政策を切り替えたことから現在は、ミニマム・アクセス米の枠外であっても実行関税率204.3%を支払えば、誰でも自由に輸入することが出来る形となっています。
今回の価格高騰により、政府によるコメ農家保護政策の不備を指摘する声が上がっています。しかしながらコメ不足を引き起こしている根本原因は、コメの国内消費量の激減にあります。図版の通り、62年 (昭和37年) には年間118.3キロであった国民一人あたりの消費量は、昨年度には19.8キロにまで下がっています。そのため1956年 (昭和31年) に332.0万ヘクタールだった水田面積は、2022年 (令和4年) には235.2万ヘクタールにまで減少。コメ農家の高齢化など様々な要因はあるにせよ、過去半世紀で食生活における需給バランスが大きく様変わりしたことが最大の引き金となっていることは言を俟ちません。
日本人の食卓がバラエティ豊かになるにつれパンや麺類の需要が増え、コメが主食であった時代はとうの昔に終わりを告げています。持続可能な生産業者としてコメ農家を救済したければ、まずは「米を喰う」。これ意外の方策はありません。食料自給率を云々する前に、自らの食生活を見直すことが肝要でしょう。

農林水産省 令和3年度食料需給表(令和4年度8月)
輸入米、恐れるに足らず。コメ信仰の強い私たち日本人は、短粒種のジャポニカ米がすべてだと思い込んで来ました。しかしながらチャーハンやガパオライス、ナシゴレンなどにはパラパラと炊き上がるインディカ米の方が遙かに美味しく仕上がります。また、あられやせんべいといった米菓や米粉製品を含むコメ加工品に至っては、輸入米であろうが砕米が原料であっても何ら問題はありません。レシピやシチュエーションによってコメの種類を使い分ける。こうした生活の知恵がこれからの日本の食卓には求められています。それはかつて国府田敬三郎が、ジャポニカ米を生産しながらも米国の需要にマッチした中粒種を選択したのと同じ生き残り作戦とも云えるでしょう。

米カリフォルニア産のカルローズ米「かろやか」